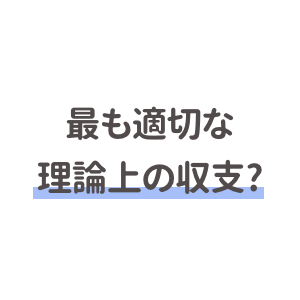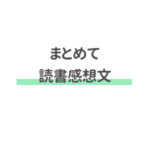追記 最初は「最も適切な理論上の収支」ってないの? というタイトルでだしていたのですが、日本語おかしいなと思いタイトルを変更しましたが、アイキャッチはめんどいし履歴にもなるのでそのまま。

この日本製鉄の記事を見かけて「おや?」と思ったことがあります。※有料記事
というか時々思ってはいたのですが、改めてですね。
利益だけ見ても良いのか悪いのか何なのかわからないので決算短信↓を見ると
売上 約8兆円
経常利益 約9,000億円
ということのようで経常で10%を超えていますね。普通に素晴らしいし、この規模でこの利益率というのもすごいなー。レガシー産業バンザイ。
https://www.nipponsteel.com/ir/library/pdf/20230510_500.pdf
もう一つ、似ているというか、同じ感覚を受ける例
日本郵政の業績ですね。
売上約11兆円に対して経常利益が約1兆円、こちらも約10%の経常利益率で単独の企業の業績としては素晴らしいとしか。
個人的にはどちらかというと日本製鉄の方により「おや?」となりますが、本質的には同じかなと思います。
例を2つ出したところでその「おや?」ってなんだよという話ですが、おや?あとの文章を一文で書くと
「おや?そんなに利益が出たら売値下げてねって言われて断る理由も説明難しくて究極的には利益額や利益率は理論値に収斂するはずでは?」
ということです。
↑で日本製鉄の方によりおや感(カギカッコ毎回かくのめんどくて以下、おや感とします。)がある、というふうに考えたのもちゃんとした理由があって、日本製鉄のビジネスは工業の材料としての金属の輸入・加工・卸のようなBtoBのビジネスだと思われますので、営業/調達の現場では
調達マン「御社の決算拝見しましたよ。絶好調ですね〜。」
営業マン「大変ありがたいことに。皆様のお陰様です。」
調達マン「ウチは値上げ頑張るけどなかなかデフレマインドが抜けないから、3%値引きお願いできません?」
営業マン「おっしゃることはよくわかります。ただ弊社も資源高との戦いもあるしいざというときに供給できない事態をヘッジするために在庫積み増してるんですよねー。」
調達マン「じゃ2%引きで」
営業マン「・・・わかりました。稟議上げてみますが難しいかもしれません。」
みたいなことが起こり得ますよね。
売上時点で2%減ると言うことがおこると8兆円に対しての2%になるので、1,600億、経常利益に対してだと約18%が減るので売値の2%引きは大きな問題であることは容易に推察できます。
一方で日本郵政はまあ、いろいろと法律があるというのもありますが、一般市民がオタク1兆円も利益出てるなら切手安くしてよ、と個別にいってくるということはあまりないと思いますので、値下げ圧力としては比較するとかなり弱いのではないかなと思います。が、どちらにしても圧力はかかるはずだよなと思います。
つまり結局おや感の中身をちゃんと追っていくと、現在の公開市場における適切な開示が行われている環境下では、「最も適切な理論上の収支」というのがあるのではないか。ということです。
一般論として大企業の経常利益が10%を超えていると業績優秀だと言われていると若かりし頃に学んだのですが今でもそうなのかなと思い軽くググると、
大企業の平均で4.34%という公的機関の情報が出てきたので、やはり今でもそうなんだよなと。
製造業と非製造業でも違いがあるようですし、日本製鉄の例を取ると製造業向け材料加工業なので、原材料市場にも左右される点ももちろん考えなければならないので、そこまで単純な話ではないことも当然理解しております。
実際数年前には4,400億円!の赤字も出していますので。(まあこれはおそらく特損でしょうけど。今回はそこは掘らない。
そう考えたとしても日本製鉄の決算説明資料にある言葉を借りると「実力ベース」どの程度利益を創出できそうか、ということに関しては会社側も常に試算しては見直しを繰り返していると思いますので、この「実力ベース」がその「最も適切な理論上の収支」なのでしょうか。
残念ながら、そこまでの巨大企業の経営の現場などを拝見したことはないのでわからない、というのが本当のところなのですが、わからないよね〜だとつまらないので個人的な考えを書き付けておくことにします。
正直、今回取り上げた2社ともに過剰利益だと思っています。
設備の維持、最新設備への一定ペースでの更新、在庫の積み増しによる中期的供給安定化、人材の継続的採用育成、株主への還元などに必要な費用分と+αを稼ぎだしたらそれ以上は必須の利益ではないと思うんですよね。
具体的に今回挙げてみた2社の「最も適切な理論上の収支」がいくらなのかは外から見える情報では算出不可能なのですが、それにしても経常利益率10%は通常に考えてとりすぎになってしまうため、本来の市場原理からすると、単年度ではそのような利益が出ても、数年のうちに「最も適切な理論上の収支」に収斂するはず?べき?可能性があるという前提で見るのが筋というものではないかなと。
一方で公開企業は株主からの成長圧力などもありますので、IR資料に載せるメッセージとしては
・こういう新しい事業や研究開発に資金を投じてさらなる利益向上を目指します。
のようにならざるを得ないのもわかります。
こういう問題を研究対象にしている研究者もいらっしゃると思いますので、書籍でも探してみようかな。
経営学というのだろうか、、この分野。経済学??
おしまい
今回はレガシー産業の好決算は大丈夫なん?と思ったのでこのような話の向きになりましたが、新興市場での好決算は別軸評価になるよね。とも考えています。まあ、レガシー産業ほどの金額規模感がある新興市場企業は少ないので、巨大化したら大体同じところに行き着くのでは、という結論もありえますが、後日同じ視点からGoogleとかマイクロソフトとか見てみようと思います。
おや感、結局端折ることを決めてから2回しかでてこなかった。。
ではまた〜。